�g21�i106-140�j
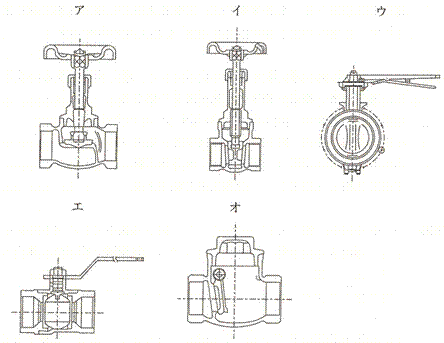 |
||
���z�����q���Ǘ���ɂ�����,�r�����̐��|��,[�@ �A�@�@]�ȓ����Ƃ�1��,����ɍs�����ƂƋK�肳��Ă���B�܂�,��Ƃɓ������Ă�,�ŏ��Ɏ_�f�Z�x��[�@�@�C �@]�ȏ�,�������f�Z�x��[�@�@�E�@�@]�ȉ��ł��邩���肵,�m�F���Ă����Ƃ��s���B
�@�@
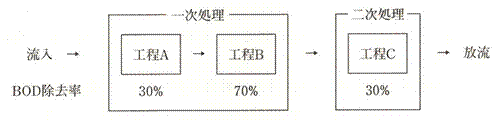 |
||
| ���z�����q���Ǘ��Z�p������������ | ||||||||||||||
| HOME | �v�Z��� | �}�E�O���t��� | �@ | |||||||||||
�g21�i106-140�j |
||||||||||||||
| ���106 | ���r���ݔ��̊Ǘ��Ɋւ���p��ƒP�ʂƂ̑g�����Ƃ���,�ł��s�K���Ȃ��͎̂��̂����ǂꂩ.
|
|||||||||||||
| �i1�j | ���̖��x
------------- m3/�s
|
|||||||||||||
| �i2�j | ���̏������\
------ mg/L |
|||||||||||||
| �i3�j | ���M���u�̔\��
-------- kW |
|||||||||||||
| �i4�j | �������C�I��
----------- mg/L |
|||||||||||||
| �i5�j | ���c���W�� ------------ 1/�� | |||||||||||||
| ���107 | �����y�єr���̊Ǘ��Ɋւ���p��̐����Ƃ���,�ł��s�K���Ȃ��͎̂��̂����ǂꂩ.
|
|||||||||||||
| �i1�j | �w��
---------------------- |
�|���v�̋z�����ݑ��ɂ����鈳�� | ||||||||||||
| �i2�j | �X�J��
--------------------- |
�r������,���̕\�ʂɕ��サ���Ō`�����W�܂������� | ||||||||||||
| �i3�j | ��������
------------------ |
�㐅,�㎿��,�G�p�����ɑΉ����ċ������邱�� | ||||||||||||
| �i4�j | �������@
------------------ |
����������v�ȍ\���v�f�ƂȂ��Ă��閌�𗘗p���ĉ���������������@ | ||||||||||||
| �i5�j | �o���L���O ----------------- | �������D�̒P�ʏd�ʓ�����̑̐ς���������,���~���錻�� | ||||||||||||
| ���108 | �����ݔ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ.
|
|||||||||||||
| �i1�j | ��h�ɓ��̔��Ɨp��������,100�l����҂ɂ��̋��Z�ɕK�v�Ȑ��������������,���͐l�̐����̗p�ɋ�����1���ő勋���ʂ�20m3������̂�,�����Ƃ��Đ�p�����ɊY������.
|
|||||||||||||
| �i2�j | �z���ǂ��狋���ǂɕ���ӏ��ł̔z���ǂ̍ŏ���������,150kPa�ȏ���m�ۂ���. | |||||||||||||
| �i3�j | �����@�Ɋ�Â�������ɂ����鉔�y�т��̉������̊�l��,0.1mg/L�ȉ��ł���.
|
|||||||||||||
| �i4�j | �����@�Ɋ�Â�������ɂ�����S�y�т��̉������̊�l��,0.3mg/L�ȉ��ł���.
|
|||||||||||||
| �i5�j | �ȈՐ�p�����Ƃ�,�������Ƃ̗p�ɋ����鐅������鐅�݂̂𐅌��Ƃ�����̂�,�����̗L���e�ʂ̍��v��10m3������̂�����. | |||||||||||||
| ���109 | �����̉��f���łɊւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ.
|
|||||||||||||
| �i1�j | ���f�܂̎c���̊m�F�ƔZ�x�̒�ʂ��ȒP�ɂł���.
|
|||||||||||||
| �i2�j | ���f���ł̌��ʂ�,pH�̉e�������邱�Ƃ��ł���.
|
|||||||||||||
| �i3�j | ���f���ł̌��ʂ�,�������������݂���ƒቺ����.
|
|||||||||||||
| �i4�j | ���f���ł̔������x��,���x�������Ȃ�قǑ����Ȃ�.
|
|||||||||||||
| �i5�j | ���f�������Ɣ��������,���Ō��ʂ���������. | |||||||||||||
| ���110 | �����ݔ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �����ɐݒu���钙�����̓V��,�ꖔ�͕ǂ�,���z���̍\���̂ƌ��p���Ă͂Ȃ�Ȃ�.
|
|||||||||||||
| �i2�j | ��x�f����������,�f�������狋���ǂɋt�����邱�Ƃ��N���X�R�l�N�V�����Ƃ���.
|
|||||||||||||
| �i3�j | �������������̋���������,���Ȃǂ�������,��C�ɊJ������镔�����Ȃ�����,�������̉����̂����ꂪ���Ȃ�.
|
|||||||||||||
| �i4�j | �������Ď�ǂ���̊e�K�ւ̕���ǂɂ�,����_�ɋߐڂ���������,����,�����e�Ղɍs�����Ƃ��ł��镔���Ɏ~���ق�݂���.
|
|||||||||||||
| �i5�j | �|���v����������,���ɒ������������|���v�ŕK�v�ӏ��ɒ��ڋ�����������ł���. | |||||||||||||
| ���111 | �������������������L�q�̂����A�����s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B | |||||||||||||
| �i1�j | ���O�ݒu����FRP���������́A�������ߗ������������������������ꍇ������B | |||||||||||||
| �i2�j | �X�e�����X�|�����������́A��������f�������A�C���������H���������邱�Ƃ�����B | |||||||||||||
| �i3�j | �|�����������́A�h�K�����疌���j���������{�������H���i�s����B | |||||||||||||
| �i4�j | �ؐ��������́A�i�����������̂����ꂪ����B | |||||||||||||
| �i5�j | FRP���������́A������@�B�I���x�������B | |||||||||||||
| ���112 | �����p�ق̌`��Ƃ��̖��̂Ɋւ��鎟�̑g�����̂���,�ł��K���Ȃ��̂͂ǂꂩ. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| �@ | �A | �C | �E | �G | �I | |||||||||
| �i1�j | �ʌ`�� | �d�ؕ� | ���t�g���t�~�� | �o�^�t���C�� | �X�C���O���t�~�� | |||||||||
| �i2�j | �ʌ`�� | �d�ؕ� | �o�^�t���C�� | �{�[���� | �X�C���O���t�~�� | |||||||||
| �i3�j | �d�ؕ� | �ʌ`�� | �o�^�t���C�� | �{�[���� | ���t�g���t�~�� | |||||||||
| �i4�j | �{�[���� | �ʌ`�� | �X�C���O���t�~�� | �d�ؕ� | ���t�g���t�~�� | |||||||||
| �i5�j | �{�[���� | �d�ؕ� | �X�C���O���t�~�� | �o�^�t���C�� | ���t�g���t�~�� | |||||||||
| ���113 | ���u�����ɐݒu����鐅�ʐ�����s�����߂̓d�ɖ_�Ƃ���,�ł��s�K���Ȃ��͎̂��̂����ǂꂩ.
|
|||||||||||||
| �i1�j | �g���|���v�N���p�̓d�� | |||||||||||||
| �i2�j | �����x��p�̓d��
|
|||||||||||||
| �i3�j | ������~�p�̓d�� |
|||||||||||||
| �i4�j | �萅�ʕٍ쓮�p�̓d�� |
|||||||||||||
| �i5�j | �����x��p�̓d�� | |||||||||||||
| ���114 | ���z�����q���Ǘ���Ɋ�Â������̊Ǘ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ.
|
|||||||||||||
| �i1�j | �q�����̓f������Ԃ̕ێ����m�F����.
|
|||||||||||||
| �i2�j | �������ɂ����鐅�̐F,����,�L��,�����̑��̏�Ԃɂ�苟�����鐅�Ɉُ��F�߂��Ƃ���,������Ɋւ���ȗ߂Ɍf���鎖���̂����K�v�Ȃ��̂ɂ��Č������s��.
|
|||||||||||||
| �i3�j | �V���c�����f�̑����,1�����ȓ����Ƃ�1��,����ɍs��.
|
|||||||||||||
| �i4�j | �������̐��|��,1�N�ȓ����Ƃ�1��,����ɍs��.
|
|||||||||||||
| �i5�j | �������̐��|��̐�����I����,�������y�ђ��������ɂ����鐅�ɂ���,�c�����f�̗L��,�F�x,���x,�L�C,���ɂ��Č������s��. | |||||||||||||
| ���115 | �����̊Ǘ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ.
|
|||||||||||||
| �i1�j | �������̐��Ɏg�p��������,���S�ɔr������.
|
|||||||||||||
| �i2�j | �������̏��łɂ�,�������@���̓u���V��p����.
|
|||||||||||||
| �i3�j | ���|��Ǝ��ɂ�,�Ɩ�,���C�t�@���⊷�C�_�N�g��p����.
|
|||||||||||||
| �i4�j | �����|���v�̋z�����Ɠf�o���̈��͂�,�����m�F����.
|
|||||||||||||
| �i5�j | �Ԑ���Ƃ��Ă̖h�K�܂̎g�p��,�P�v�I�ɍs��. | |||||||||||||
| ���116 | �����ݔ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ.
|
|||||||||||||
| �i1�j | �����z�Ǔ��̐����ɂ�����C�̗̂n��x��,�����̏㏸�ɂ�葝������.
|
|||||||||||||
| �i2�j | �����z�ǂɋ����ǂ�p�����ꍇ��,�����z�|���v�̏z�ʂ�������,�ԓ��ǂɂ����ĊǓ������������Ȃ�,���H�̌����ƂȂ�.
|
|||||||||||||
| �i3�j | �����ݔ��Ŏg�p��������ޗ���,���x�������Ȃ��,��ʂɕ��H���x������.
|
|||||||||||||
| �i4�j | ���C��M���Ƃ���,���M�R�C���ɂ���ċ����p�̐������M���������,�Ԑډ��M�����Ƃ���.
|
|||||||||||||
| �i5�j | �����������ݔ��ɐ݂���z�|���v��,�ȃG�l���M�[�̂��߂�,�ԓ��ǂ̉��x���ቺ�����������^�]���邱�Ƃ��D�܂���. | |||||||||||||
| ���117 | �����ݔ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ.
|
|||||||||||||
| �i1�j | ���z�ǂɂ����ĒP���̐L�k�p���p����ꍇ,�ݒu�Ԋu��20m���x�ł���.
|
|||||||||||||
| �i2�j | �������̗e�ʂ�,�s�[�N���̕K�v�e�ʂ�1�`2���ԕ���ڈ���,���M�\�͂Ƃ̃o�����X���猈�肷��.
|
|||||||||||||
| �i3�j | �G�l���M�[����W��(CEC/HW)��,�N�≼�z�������ׂ�N�ԋ�������G�l���M�[�ʂŏ������l�ł���.
|
|||||||||||||
| �i4�j | �z�|���v�̏z���ʂ�,���M���u�ɂ����鋋�����x�ƕԓ����x�Ƃ̉��x���ɔ���Ⴗ��.
|
|||||||||||||
| �i5�j | �����z���̉��ǂɂ����Ă�,�ō����Ɏ�����C�����ق�݂���. | |||||||||||||
| ���118 | �����ݔ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ. |
|||||||||||||
| �i1�j | ������(�c����)��,�����ݔ��̈��S���u�ł���.
|
|||||||||||||
| �i2�j | �����قɂ�,���M���ɖc���������������߂̊Ԑڔr���ǂ�݂���.
|
|||||||||||||
| �i3�j | ���������z�ǂɂ�,�L�k�njp����g�p����,�ǂ̐L�k�ʂ��z������.
|
|||||||||||||
| �i4�j | �����ǂɎg�p���铺�ǂ̕��H�ɂ�,�אH�ƍE�H�Ƃ�����.
|
|||||||||||||
| �i5�j | �x���[�Y�^�L�k�njp���,�X���[�u�^�Ɣ�r���ĐL�k�z���ʂ��傫��. | |||||||||||||
| ���119 | �����ݔ��̉��M���u�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �^�����������,�ʑ̓����C���ȉ��Ɍ�����,�M�}���������������̔M������ŔM�������s��,������������B |
|||||||||||||
| �i2�j | ���������������,
90���ȏ�̓����������p�Ƃ��ė��p�����B |
|||||||||||||
| �i3�j | �}���`�^�C�v�̋����@�ɂ�,�u�ԓ���������g�ݍ��킹,�e�ʐ�����s�����̂�����B
|
|||||||||||||
| �i4�j | �ї��|�C����,�ʐ��ʂ�����,��^�̃V�����[�ݔ��̋����ɓK���Ă���B
|
|||||||||||||
| �i5�j | ���M�R�C���t����������,���C�Ȃǂ̔M�}��������ꍇ�Ɉ�ʓI�Ɏg�p�����B | |||||||||||||
| ���120 | �����ݔ��̕ێ�Ǘ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �����z�ǂ�,�����n���z�ǂ̊ǐ��ɏ�����,1�N��1��,�ǐ����s���B |
|||||||||||||
| �i2�j | �����z�|���v��,
1�N��1��,����m�F�����˂ĕ��𥐴�|�����{����B |
|||||||||||||
| �i3�j | �����̂��ܕ���,
1�N��1��ȏ�̕��𐴑|���s���B |
|||||||||||||
| �i4�j | ���W�I�l���ǂ̔�����h�~���邽��,�����������ݔ��̕ԓ����x��40���ȏ�Ƃ���B |
|||||||||||||
| �i5�j | �����ق�, 1�J����1��,���o�[�n���h���𑀍삳���č쓮���m�F����B | |||||||||||||
| ���121 | �r���ʋC�ݔ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �Ԑڔr����,�r������Ԃ�݂�,��ʔr���n���ɐڑ����ꂽ�g���b�v��L���鐅�e��֊J������B
|
|||||||||||||
| �i2�j | �|������,�r�����l�܂�₷���ӏ��ɐ݂���B
|
|||||||||||||
| �i3�j | �O���[�X�j�W���,���イ�[����r�o�����r�����Ɋ܂܂���������j�~���������W���邽�߂ɐ݂���B
|
|||||||||||||
| �i4�j | �N�����̃|���v�N�������ʂ�,�ʏ�,���z���̍ʼn��K�̓�d�X���u��ʂ̏��ʂ���Ƃ���B
|
|||||||||||||
| �i5�j | ���R�������̔r�����ǂ̂����z��,�Ǔ�������0�A6�`1�A5m/S�ƂȂ�悤�ɂ���B | |||||||||||||
| ���122 | �r���ʋC�ݔ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �r�����ɂ�,�����̕ێ�_�����e�Ղɂ����S�ɍs�����Ƃ��ł���ʒu��,�ŏ����a50cm�ȏ�̉~�����ڂ��邱�Ƃ��ł���}���z�[����݂���B
|
|||||||||||||
| �i2�j | �ʋC���Ċǂ̏㕔��,�ō��ʂ̉q�����̂��ӂꉏ����150mm�ȏ㍂���ʒu��,�L���ʋC�ǂɐڑ�����B
|
|||||||||||||
| �i3�j | �����|���v��,�Œᐅ�ʈȏ�ʼn^�]��,�d���@�͎g�p��,��ɐ��v������B
|
|||||||||||||
| �i4�j | ����n�ɂ�����~�n�r���ǂ�,�����[�x���[�����݂���B
|
|||||||||||||
| �i5�j | �r������Ljȍ~�������ƂȂ�ꍇ��,�L���ʋC�����Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B | |||||||||||||
| ���123 | �r���g���b�v�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �o�g���b�v��,
�r�g���b�v�Ɣ�ׂ�,�������x���������B |
|||||||||||||
| �i2�j | �����Ɋ܂܂�鉘���Ȃǂ��t����,���͒��a���Ȃ��\���Ƃ���B
|
|||||||||||||
| �i3�j | �����ɂ��,�r���Ǔ��̏L�C�@�q���Q�����̈ړ���L���ɖh�~�ł���悤�ȍ\���Ƃ���B
|
|||||||||||||
| �i4�j | �r�f�ʐϔ�i���o�r�f�ʐ�/�����r�f�ʐ�)���傫����,�������x�͑傫���Ȃ�B |
|||||||||||||
| �i5�j | ��ʂɕ����[�́B
50mm�ȏ�100mm�ȉ��Ƃ���B |
|||||||||||||
| ���124 | �J���r���ݔ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �J���܂��ɂ́B�D���߂�݂���B
|
|||||||||||||
| �i2�j | �J������ǂ́B�܂�����č������~�n�r���ǂɐڑ�����B
|
|||||||||||||
| �i3�j | �J�����Ċǂ�r�����Ċǂƌ��p������B
|
|||||||||||||
| �i4�j | ���[�t�h�����̃X�g���[�i��,�������˂��o���h�[���^��p����B
|
|||||||||||||
| �i5�j | �n�����̓H����}�邽�߂�,�J���Z���������̗p����B | |||||||||||||
| ���125 | �r���ʋC�ݔ��̕ێ�Ǘ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �������ɂ��z�ǂ̐��|�ł�,
5�`30MPa�̍����̐��˂���B |
|||||||||||||
| �i2�j | �r���|���v��,�_�����Ƀ��J�j�J���V�[������������B
|
|||||||||||||
| �i3�j | ���イ�[�r�����̐��ʐ���ɂ�,�d�ɖ_���p������B
|
|||||||||||||
| �i4�j | �r���|���v��,1�J����1��,�≏��R�̑�����s��,1M���ȏ�ł��邱�Ƃ��m�F����B
|
|||||||||||||
| �i5�j | �X�l�[�N���C����ʂ����@��,�O���[�X�Ȃǂ̌ł��t�����̏����ɓK���Ă���B | |||||||||||||
| ���126 | �r�����̐��|�Ɋւ��鎟�̕��͂�[�@�@�@�@]���ɓ�����̑g�����Ƃ���,�ł��K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B ���z�����q���Ǘ���ɂ�����,�r�����̐��|��,[�@ �A�@�@]�ȓ����Ƃ�1��,����ɍs�����ƂƋK�肳��Ă���B�܂�,��Ƃɓ������Ă�,�ŏ��Ɏ_�f�Z�x��[�@�@�C �@]�ȏ�,�������f�Z�x��[�@�@�E�@�@]�ȉ��ł��邩���肵,�m�F���Ă����Ƃ��s���B |
|||||||||||||
| �A�@�@ �C�@�@�@�@�@ �E | ||||||||||||||
| �i1�j | 1�N -------
16% ------- 10������ |
|||||||||||||
| �i2�j | 1�N -------
16% ------- 15ppm |
|||||||||||||
| �i3�j | 1�N -------
1�W% ------- 15ppm |
|||||||||||||
| �i4�j | �U���� -----
1�W% ------- 10ppm |
|||||||||||||
| �i5�j | �U���� ----- 1�W% ------- 15ppm | |||||||||||||
| ���127 | �r���ݔ��̊Ǘ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �O���[�X�j�W��̃O���[�X��,
7�`10����1��̊Ԋu�ŏ�������B |
|||||||||||||
| �i2�j | ���イ�[�r������,���D���\�������ł���悤��,�|���v�̉^�]��~���ʂ���������B
|
|||||||||||||
| �i3�j | �r�����ɂ�����,���C�y�ъh�q���s��,���L�̔����y�уX�J���Ȃǂ̌Œ�����h�~����B
|
|||||||||||||
| �i4�j | �r���|���v�̓���_���ł�,�d���l�̐U�ꕝ�ɒ��ӂ���B
|
|||||||||||||
| �i5�j | �ʋC�ق�,����������̂�,����I�ɓ_������B | |||||||||||||
| ���128 | �q�����ݔ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | ���֊��������,��ʂɐ�����,���ٕ����y�ю����T�C�z��������3�ɕ�������B
|
|||||||||||||
| �i2�j | ��֊�̂���,�u���[�A�E�g����,�[�b�g�����������͂ɕ��o����,���̐����ʼn����𐁂�����悤�ɔr�o��������ł���B
|
|||||||||||||
| �i3�j | ���j�b�g���ɂ��,�h�������y�ї{�����y�������B
|
|||||||||||||
| �i4�j | ��֊���ق̕K�v�Œᓮ������,
70kPa�ł���B |
|||||||||||||
| �i5�j | �T�C�z���[�b�g������֊��,�����ʂ̐��ʂ̍��܂�ɂ�鐅�̗����𗘗p���ĉ����������o���B | |||||||||||||
| ���129 | �q�����ݔ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �㎿�������ݔ���,���f����������Ă��܂��ꍇ��,���f�������s���B
|
|||||||||||||
| �i2�j | �������֍���,�����ǂ�ڑ����Đ��ɓK�������x�܂ʼn��M�������������B
|
|||||||||||||
| �i3�j | �������Ƃ�,�g�p��������r���n���ɓ������߂ɗp��������ł���,
|
|||||||||||||
| �i4�j | �ߐ��@�������ꍇ��,�f���ʂ̍팸�����łȂ�,�r���Ǔ��̗��������Ȃǂɔz������B
|
|||||||||||||
| �i5�j | ��֊���قɂ�,�o�L���[���v���[�J�����t����B | |||||||||||||
| ���130 | ���r���q���ݔ��Ɏg�p����@��y�єz�ǂɊւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �{�[���ق�,��R���傫�����ʒ���������B
|
|||||||||||||
| �i2�j | �����ق�,1�����̈��͂�,2�����Őݒ肵�����͂܂ʼn����铭��������B
|
|||||||||||||
| �i3�j | �d���ق�,�}�~����̂�,�E�I�[�^�n���}�̔����ɒ��ӂ���B
|
|||||||||||||
| �i4�j | ���z�Ǘp�����߂����|�ǂ�,�������p�z�ǂɂ͒ʏ�p�����Ȃ��B
|
|||||||||||||
| �i5�j | �S�R���N���[�g�ǂ�,�~�n���ł͖��݂ŊO�����傫���ꍇ�Ȃǂɗp������B | |||||||||||||
| ���131 | �G�p���Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �G�p�������ݔ���,��,�|���v,�z�Ǘ�,���[�̋���������\�������B |
|||||||||||||
| �i2�j | �G�p���̗��p�ɂ����,�㐅�g�p�ʂ��팸�����B
|
|||||||||||||
| �i3�j | �G�p���̔z�ǂ�,�㐅�ǂƈقȂ�F�œh������B
|
|||||||||||||
| �i4�j | �ʏz�����̎G�p���̗��p�ɂ��,�������ւ̕��S���y�������B
|
|||||||||||||
| �i5�j | ���z�����q���Ǘ���ł�,�����֏��p���̐�����̍��ڂƂ���,���x���K�肵�Ă���B | |||||||||||||
| ���132 | ���イ�[�r�����Q�{�݂Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | ���イ�[�r����BOD�y��SS�Z�x��,�����r���������Z�x�ł���B
|
|||||||||||||
| �i2�j | �������ꂽ����,�G�p���̌����Ƃ��ė��p�\�ł���B
|
|||||||||||||
| �i3�j | ���㕪���@�ł�,�r���̖��x�Ɩ����̖��x�Ƃ̍����傫��,�����̒��a���������قǕ��㑬�x�������Ȃ�B
|
|||||||||||||
| �i4�j | ���������@��,���㕪���@�ɔ�ׂĔ������D�ʂ����Ȃ��X���ɂ���B
|
|||||||||||||
| �i5�j | ���������@��,�y��ۂ�������ۂ�p�����������@�ł���B | |||||||||||||
| ���133 | �G�p���ݔ��̈ێ��Ǘ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �r���ė��p����,���f���łȂǂ̑[�u���u����B
|
|||||||||||||
| �i2�j | �����֏��̗p�ɋ�����G�p���ɂ����Ă�,�咰�ۂ̌�����2�J���ȓ����Ƃ�1��,����ɍs���B
|
|||||||||||||
| �i3�j | �G�p�����́A�����̐����ؗ����Ȃ��悤�ȑ[�u���u����B
|
|||||||||||||
| �i4�j | �U����C�i���͐��|�̗p�ɋ�����G�p���ɂ����ẮA
pH�A�L�C�O�ϋy�їV���c�����f�̑����,1�J���ȓ����Ƃ�1��,����ɍs���B |
|||||||||||||
| �i5�j | �X�P�[���̕t���ɂ��,�Ǔ���ǂ����邨���ꂪ����B | |||||||||||||
| ���134 | ���ɂ����鍂�x�����ŏ����ΏۂƂ��镨���Ƃ��̏����@�Ƃ̑g�����Ƃ���,�ł��s�K���Ȃ��͎̂��̂����ǂꂩ�B �@�@ |
|||||||||||||
| �����Ώە����@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�����@ | ||||||||||||||
| �i1�j | ���V���̎c���L�@����
----- �}������ߖ@ |
|||||||||||||
| �i2�j | ���f������
-------------- �����w�I�ɉ��@�y�ѐ����w�I�E���@ |
|||||||||||||
| �i3�j | �n�𐫂̎c���L�@����
----- �����Y�z���@ |
|||||||||||||
| �i4�j | ����������
--------------- ���w�I�_���@ |
|||||||||||||
| �i5�j | �A�����j�A --------------- �C�I�������@ | |||||||||||||
| ���135 | ����3�̏����H������Ȃ���ɂ�����S�̂�BOD�������Ƃ���,�ł��߂��l�͂ǂꂩ�B |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| �i1�j | 65�� |
|||||||||||||
| �i2�j | 70�� |
|||||||||||||
| �i3�j | 85�� |
|||||||||||||
| �i4�j | 90�� |
|||||||||||||
| �i5�j | 95% | |||||||||||||
| ���136 | ������ʓI���p�����Ă����������������������L�q�̂����A�����s�K���Ȃ��̂����̂����ǂꂩ�B | |||||||||||||
| �i1�j | �L�@�n���f���Ƃ��āA���f���C�\�V�A�k�[���_���p�����Ă���B | |||||||||||||
| �i2�j | ���������Y�����́A�����y�������Ȃǂ��e�������B | |||||||||||||
| �i3�j | ���@�n���f�����L�@�n���f�����������g�p���Ă͂Ȃ�Ȃ��B | |||||||||||||
| �i4�j | �������ɂ����������������Ƃ��āA�c�����f�����o����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B | |||||||||||||
| �i5�j | ��������������n�����x�́A���@�n���f������L�@�n���f�������������B | |||||||||||||
| ���137 | �Ћy�я��Ɋւ�����Ƃ��̐����Ƃ̑g�����Ƃ���,�ł��s�K���Ȃ��͎̂��̂����ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | ��ʉ� ---
�؍ޥ�����̈�ʓI�ȉR���̉� |
|||||||||||||
| �i2�j | ��p���� ---
�M��D������ |
|||||||||||||
| �i3�j | �������� ---
�_�f�̋��������� |
|||||||||||||
| �i4�j | ������ ---
���A�S�ޓ��̋������o�����鍂���̉� |
|||||||||||||
| �i5�j | �������� --- �R��������������� | |||||||||||||
| ���138 | ���h�@�Ɋ�Â����ΐݔ��̓_���Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | ����h�ΑΏە��ɂ�����@�����_���̌��ʂƂ��̕s���Ɋւ��鐥���[�u�̕�,1�N�ɉ�ł���B
|
|||||||||||||
| �i2�j | ���h�p�ݔ��Ȃǂɕ��u����鎩�Ɣ��d���u��,1�N��1��쓮�_�����s���B
|
|||||||||||||
| �i3�j | �X�v�����N���[�ݔ��ɂ��Ă�,�w�b�h�̕ό`�⑹�������̓_�����ڂƂ���B
|
|||||||||||||
| �i4�j | �������ΐ�ݔ���1�N��1��쓮����,
�_����ɏ]��,�����I�ɋ@�\�̓_�����s���B |
|||||||||||||
| �i5�j | ����p�r�h�ΑΏە���,�h�ΑΏە��_�����i�҂��_����,����B | |||||||||||||
| ���139 | �K�X�ݔ��Ɋւ��鎟�̑g�����̂���,�ł��s�K���Ȃ��̂͂ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | �K�o�i ------------------- | �ً}����,���u���얔�͎����I�ɃK�X���Ւf���鑕�u��,��K�͂Ȓn���X�Ȃǂɐݒu���`���t�����Ă���B | ||||||||||||
| �i2�j | �}�C�R�����[�^ -------------- | �k�x5�������ȏ�̒n�k�����m�������I�ɃK�X���Ւf����ۈ��@�\�������Ă���B | ||||||||||||
| �i3�j | �����݊ǃK�X�Ւf���u ------- | ���z���ւ̃K�X�����݊ǂɐݒu����,�ً}���ɒn�ォ��̑���ɂ��K�X�������Ւf����B | ||||||||||||
| �i4�j | �q���[�Y�K�X�� ------------- | �ߑ�ɃK�X���R���ƃK�X����K�X�̃{�[���������オ��,�����I�ɃK�X�̗�����~������B | ||||||||||||
| �i5�j | �K�X�R���x��� ------------ | �K�X�R������m��,�x����x������̂ł���,�K�X�̎�ނɂ��ݒu�ꏊ���قȂ�B |
||||||||||||
| ���140 | �����@�Ɋ�Â�������Ɋւ���ȗ�(����15�N�����J���ȗߑ�101��)�ɋK�肷���Ƃ���,����Ă�����͎̂��̂����ǂꂩ�B
|
|||||||||||||
| �i1�j | ��ʍ�
---------- 1mL�̌����Ō`�������W������100�ȉ��ł��邱�� |
|||||||||||||
| �i2�j | ���x
-------------- 5�x�ȉ��ł��邱�� |
|||||||||||||
| �i3�j | ���y�т��̉����� ---
1�A0mg/L�ȉ��ł��邱�� |
|||||||||||||
| �i4�j | pH�l
------------- 5�A8�ȏ�8�A6�ȉ��ł��邱�� |
|||||||||||||
| �i5�j | �咰�� ------------ ���o����Ȃ����� | |||||||||||||
| ��106�`140 | HOME | |
|---|---|---|
| �@���@1�`20 | ���@21�`45 | ���@46�`90 |
| ���@91�`105 | ���@141�`165 | ���@166�`180 |
| �g�E23�i106�`140�j | �g�E22�i106�`140�j | �g�E20�i106�`140�j | �g�E19�i106�`140�j |
|---|