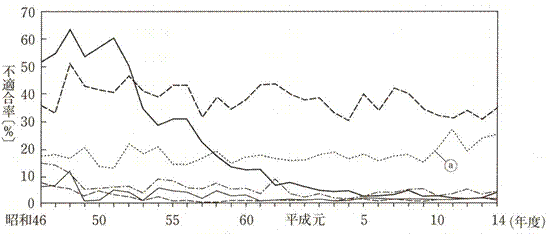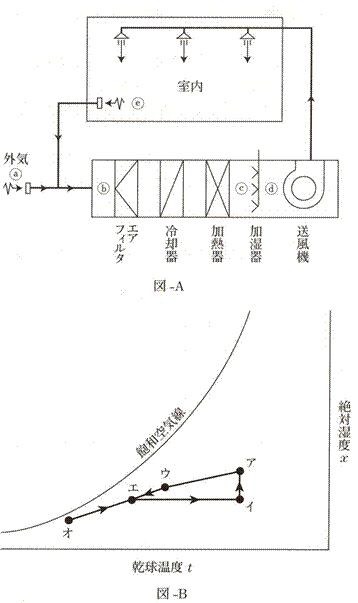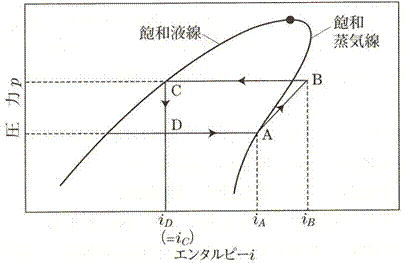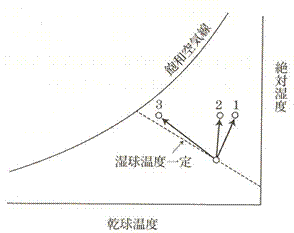| 建築物環境衛生技術管理者試験に挑戦 |
|
| HOME |
計算問題 |
図・ブラフ問題 |
|
|
H20(46-90)
|
| 問題46 |
次の用語とその単位との組合せとして、誤っているものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
熱伝導抵抗
------ m・K/W
|
|
|
|
|
(2) |
電気抵抗
------- Ω |
|
|
|
|
(3) |
色温度
--------- K |
|
|
|
|
(4) |
輝度
----------- cd/m2 |
|
|
|
|
(5) |
音の強さ
------- w/m2 |
|
|
|
|
|
| 問題47 |
壁体における熱移動に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
固体内を流れる単位面積当たりの熱流は、温度こう配に比例する。
|
|
|
|
|
(2) |
壁と壁表面に接する空気との間の単位面積当たりの熱流は、壁表面温度と空気温度の差と対流熱伝達率の積で表される。 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
熱貫流抵抗は、壁体の内表面及び外表面の熱伝達抵抗、固体壁の熱 伝導抵抗、中空層の熱抵抗の合計で表される。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
総合熱伝達率は、対流熱伝達率と放射熱伝達率の和で表される。 |
|
|
|
|
(5) |
物体表面から射出される単位面積当たりの放射熱流は、放射率とシュテファン・ボルツマン定数と物体表面の絶対温度との積で表される。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題48 |
次に示す用語とその数値との組合せとして、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
白色ペイントの長波長放射率
----- 0.2
|
|
|
|
|
(2) |
20℃
の空気の飽和絶対湿度 ---- 0.015 kg/ kg ( DA) |
|
|
|
|
(3) |
常温空気の密度
-------------- 1.2 kg/m3 |
|
|
|
|
(4) |
コンクリートの熱伝導率
--------- 1.3W/(m・K) |
|
|
|
|
(5) |
黒色ペイントの日射吸収率
------ 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題49 |
熱貫流率5.0W/(m2・K)の壁を隔てて、室内温度20℃
、室外温度0℃ のとき、壁の室内側表面温度に最も近いものは次のうちどれか。ただし、室内側熱伝達率を9W/(m2・K)、室外側熱伝達率を23W/(m2・K)とする。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
16℃
|
|
|
|
|
(2) |
11℃ |
|
|
|
|
(3) |
10℃ |
|
|
|
|
(4) |
9℃ |
|
|
|
|
(5) |
4℃ |
|
|
|
|
|
| 問題50 |
流体の基礎に関する次の文章の「
」内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
流れの「 ア 」を仮定すると以下の式が得られる。
1/2ρU2+P+pgh=一定
左辺第一項を[ イ ]第二項を静圧、第三項を[ ウ ]と呼ぶ。
ただし、ρ:密度、U:速度、P:圧力、g:重力加速度、h:高さ。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
運動エネルギー保存
---- 位置圧 ---- 動圧
|
|
|
|
|
(2) |
運動エネルギー保存
---- 動圧 ----- 位置圧 |
|
|
|
|
(3) |
連続条件
------------- 絶対圧 --- 動圧 |
|
|
|
|
(4) |
連続条件
------------- 動圧 ----- 位置圧 |
|
|
|
|
(5) |
連続条件
------------- 動圧 ----- 絶対圧 |
|
|
|
|
|
| 問題51 |
次に示すア〜工の室について、第三種換気方式が適していない組合せはどれか。
ア. 塗装作業をしている室 イ. クリーンルーム ウ. 汚物処理室 工. 手術室
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
ア と イ
|
|
|
|
|
(2) |
ア と ウ |
|
|
|
|
(3) |
ア と エ |
|
|
|
|
(4) |
イ と エ |
|
|
|
|
(5) |
ウ と エ |
|
|
|
|
|
| 問題52 |
床面積20m2、天丼高さ2.5mの喫煙室での1時間当たりのたばこの喫煙本数が5本である場合に、室内の粉じん濃度を0.10
mg/m3とするのに必要な最小の外気による換気回数として正しいものは次のうちどれか。ただし、たばこ1本当たりの粉じん発生量は10
mg、外気の粉じん濃度は0.05 mg/m3であり、たばこ以外の粉じん発生、壁面への吸着などの影響は無視できるものとする。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
1回/h
|
|
|
|
|
(2) |
10回/h |
|
|
|
|
(3) |
20回/h |
|
|
|
|
(4) |
50回/h |
|
|
|
|
(5) |
1,000回/h |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題53 |
下の図は、東京都における建築物環境衛生管理基準の空気環境の調整の項目について、不適合率の経年変化を示したものであるが、(a)に該当する項目は次のうちどれか。
|
|
|
|
|
|
|
|
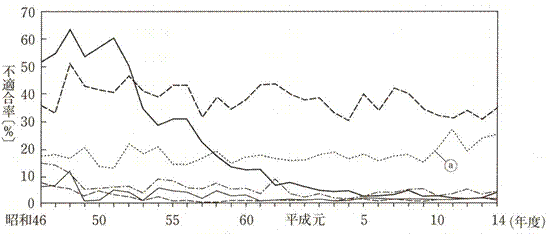 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
気流
|
|
|
|
|
(2) |
相対湿度 |
|
|
|
|
(3) |
一酸化炭素 |
|
|
|
|
(4) |
二酸化炭素 |
|
|
|
|
(5) |
浮遊粉じん |
|
|
|
|
|
| 問題54 |
室内温湿度と気流に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
室内相対湿度は、室内温度が上昇すると増加する。
|
|
|
|
|
(2) |
室内温度は、変動の幅が小さく、安定していることが望ましい。 |
|
|
|
|
(3) |
鉛直方向の温度差は、上下温度差として表される。 |
|
|
|
|
(4) |
極端な低気流は、温度の不均一な分布をもたらしやすい。 |
|
|
|
|
(5) |
建築物環境衛生管理基準における気流の基準値は、不快な冷風気流を考慮して定められている。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題55 |
冬季における結露に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
家具の後ろや押入れでは、表面結露を起こしやすい。
|
|
|
|
|
(2) |
外断熱を施すと、内部結露が発生しにくい。 |
|
|
|
|
(3) |
壁体の熱橋部分では、表面結露を起こしにくい。 |
|
|
|
|
(4) |
室内の絶対湿度を下げると、結露が発生しにくい。 |
|
|
|
|
(5) |
壁体内部の室内側に防湿層を設けると、内部結露が発生しにくい。 |
|
|
|
|
|
| 問題56 |
換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
換気回数とは、換気量を室容積で除したものである。
|
|
|
|
|
(2) |
一人当たりの必要換気量は、呼吸による酸素の消費量を基準として求めることが多い。 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
換気の目的には、酸素の供給、室内空気の浄化、熱・水蒸気の排除等がある。 |
|
|
|
|
(4) |
開放型燃焼器具の必要換気量は、燃料消費量を用いて算出する。 |
|
|
|
|
(5) |
自然換気は、風力又は室内タト温度差により行われる。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題57 |
室内空気汚染物質とその発生源との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
一酸化炭素
------- 駐車場からの排気
|
|
|
|
|
(2) |
二酸化炭素
------- 人の活動 |
|
|
|
|
(3) |
ラドンガス
--------- 燃焼器具 |
|
|
|
|
(4) |
ホルムアルデヒド ---
建材 |
|
|
|
|
(5) |
浮遊粉じん
-------- 外気由来 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題58 |
室内における次の汚染物質のうち、たばこ煙が発生源とならないものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
浮遊粉じん |
|
|
|
|
(2) |
オゾン |
|
|
|
|
(3) |
二酸化炭素 |
|
|
|
|
(4) |
一酸化炭素 |
|
|
|
|
(5) |
窒素酸化物 |
|
|
|
|
|
| 問題59 |
暖房時における単一ダクト方式の空気調和システムを図-Aに示す。
図-Bは、図-A中の(a)〜(e)における空気の状態変化を湿り空気線図上に表したものである。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
図-A中の(d)に相当する図-B中の状態点は、次のうちそれか。 |
|
|
|
|
|
|
(1) |
ア |
|
|
|
|
(2) |
イ |
|
|
|
|
(3) |
ウ |
|
|
|
|
(4) |
エ |
|
|
|
|
(5) |
オ |
|
|
|
|
|
| 問題60 |
湿り空気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
水蒸気分圧とは、空気中の水蒸気が示す分圧のことである。 |
|
|
|
|
(2) |
飽和度とは、空気中の水蒸気の質量を、同じ空気中の乾き空気の質量で除したものである。 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
相対湿度とは、ある空気の水蒸気分圧とその空気と同一温度の飽和水蒸気分圧との比を百分率で示したものである。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
熱水分比とは、比エンタルピーの変化量と絶対湿度の変化量との比である。 |
|
|
|
|
(5) |
露点温度とは、湿り空気を冷却したとき飽和状態になる温度のことである。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題61 |
建築物の熱負荷に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
照明やOA機器からの室内発熱負荷は、顕熱負荷である。 |
|
|
|
|
(2) |
すきま風の熱負荷は、潜熱負荷と顕熱負荷である。 |
|
|
|
|
(3) |
ガラス窓面積の大きい建築物におけるペリメータゾーンでは、冬期でも冷房負荷が発生することがある。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
ポンプや送風機に加えられる動力は、熱負荷として考慮する。 |
|
|
|
|
(5) |
ダクトや配管の熱負荷は、無視する。 |
|
|
|
|
|
| 問題62 |
空気調和設備の冷暖房負荷に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
断熱性が高く、窓部の日射遮へい性が高い場合には負荷変動が穏やかになるので、ペリメータゾーンとインテリアゾーンに分離しないことがある。 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
冷房最大負荷計算において、照明発熱は通常、室使用時間帯に継続して100%点灯していると考えて設計してよい。 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
OA化の進んだ事務スペースでは、OA機器からの発熱量は、40〜80W/m2程度のものが計画される。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
人体からの発熱のうち、人体表面からの対流及び放射によって放熱されるのは潜熱負荷である。 |
|
|
|
|
|
|
(5) |
大規模多層建築物では、複数階にまたがる垂直方向の空気調和のゾーニングが行われる。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題63 |
熱負荷計算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
ダクトの寸法、空気調和機及び熱源装置の容量を決めるために、最大熱負荷を計算する。 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
建築物の外壁を通過して侵入する熱量は、内外空気温度差と壁の熱伝導率を乗じて算出する。 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
使用時間が昼間の建築物には、一般に8〜17時の設計外気条件が用いられる。 |
|
|
|
|
(4) |
最大負荷は、複数の時刻の算定結果を比較して決定する。 |
|
|
|
|
(5) |
設計用外気温度には、一般にTAC温度が用いられる。 |
|
|
|
|
|
| 問題64 |
空気調和方式と設備の構成に関する次の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。 |
|
|
|
|
|
|
(1) |
変風量単一ダクト ---------------- 混合ユニット |
|
|
|
|
(2) |
定風量単一ダクト ---------------- 還気ダクト |
|
|
|
|
(3) |
水熱源ヒートポンプ方式
----------- 冷却塔 |
|
|
|
|
(4) |
放射冷暖房方式 ----------------- 天井パネル |
|
|
|
|
(5) |
ダクト併用ファンコイルユニット方式 --- 冷温水配管 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題65 |
地域冷暖房に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
排熱や未利用エネルギーの活用により、省エネルギーが図れる。 |
|
|
|
|
(2) |
個別熱源に比べ、一般に環境負荷は増加する。 |
|
|
|
|
(3) |
21GJ/h以上の熱媒体を不特定多数の需要家に供給する能力を持つ施設は、熱供給事業法の適用を受ける。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
熱源の集中により都市防災に寄与する。 |
|
|
|
|
(5) |
需要家では、スペース削減が図れる。 |
|
|
|
|
|
| 問題66 |
下の図は、蒸気圧縮サイクルの原理をモリエール(圧カエンタルピー)線図上に示したものである。蒸気圧縮サイクルに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
A→
Bでは、液化した冷媒を圧縮機にて、圧縮する。 |
|
|
|
|
(2) |
B→
Cでは、凝縮器で高圧・高温の蒸気を冷却・液化し、外部へ熱を放出する。 |
|
|
|
|
(3) |
C→
Dでは、凝縮器で液化され受液器にためられた液冷媒を膨張弁で減圧し、低圧・低温の湿り蒸気状態とする。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
D→
Aでは、蒸発器で湿り蒸気状態の冷媒を蒸発し、外部より熱を除去する。 |
|
|
|
|
(5) |
成績係数とは、冷却熱量や加熱熱量の出力を、これに要した圧縮仕事で除したものである。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題67 |
空気調和機に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
マルチユニット型ヒートポンプシステムは、加湿器を組み込むことで、冬期の湿度調節も可能である。 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
ルームエアコンディショナには、スプリット型、一体型、簡易設置型がある。 |
|
|
|
|
(3) |
エアハンドリングユニットは、コイル、熱源装置、送風機、加湿器、エアフィルタ等から構成される。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
ファンコイルユニットは、冷却。加熱コイルとファンモータユニット及びエアフィルタ等から構成される。 |
|
|
|
|
|
|
(5) |
パッケージ型空気調和機は、送風機、空気熱交換器、圧縮器、凝縮器、エアフィルタ等から構成される。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題68 |
空気調和機に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
夏期に外気温度が高すぎる場合には、空気予冷器が用いられる場合がある。 |
|
|
|
|
(2) |
冷却器の下部には、ドレンパンが設置される。 |
|
|
|
|
(3) |
冷却器には、プレートフィン型コイルなどが用いられる。 |
|
|
|
|
(4) |
冷却器の下部には、空気抜き用のキャップが取り付けられている。 |
|
|
|
|
(5) |
再熱器は、負荷変動に応じて再加熱が必要な場合に用いられる。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題69 |
送風機に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
軸流送風機は、一般に騒音値が高い。 |
|
|
|
|
(2) |
後向き送風機は、遠心送風機の一種である。 |
|
|
|
|
(3) |
プロペラ型送風機は、小型冷却塔などに用いられる。 |
|
|
|
|
(4) |
斜流送風機は、便所などの局所換気に用いられる。 |
|
|
|
|
(5) |
横流送風機は、高速ダクト空気調和用として用いられる。 |
|
|
|
|
|
| 問題70 |
多翼送風機に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
小型で大風量を扱うことができ、空気調和用に多用されている。 |
|
|
|
|
(2) |
高速回転に適していることから、高い圧力が得られる。 |
|
|
|
|
(3) |
ダクト系への接続により、空気の脈動と振動・騒音を発生する場合がある。 |
|
|
|
|
(4) |
比較的騒音値が高く、効率は低い。 |
|
|
|
|
(5) |
風量の増加とともに軸動力が増加するため、オーバーロードに注意する。
|
|
|
|
|
|
| 問題71 |
空気調和用ダクトとその付属品に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
グラスウールダクトは、断熱が不要で吸音性がある。 |
|
|
|
|
(2) |
ステンレスダクトや塩化ビニルライニングダクトは、水蒸気や腐食性ガスのある系統に用いられる。 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
ダンパには、風量調整ダンパ、防火ダンパ、防煙ダンパ、防煙防火ダンパ、逆流防止ダンパ等がある。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
組み立てられて筒状となったダクト同士を接続するには、フランジを用いる。 |
|
|
|
|
(5) |
等速法は、ダクトの単位長さ当たりの摩擦損失が一定となるようにサイズを決める方法である。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題72 |
エアフィルタの粉じん捕集率の測定方法に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。
質量法は[ ア ]、比色法は[ イ ]、計数法は[ ウ ]の性能表示に使用される。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
中性能フィルタ ----- 高性能フィルタ ------ 粗じん用フィルタ |
|
|
|
|
(2) |
高性能フィルタ
----- 粗じん用フィルタ ----- 中性能フィルタ |
|
|
|
|
(3) |
高性能フィルタ
----- 中性能フィルタ ----- 粗じん用フィルタ |
|
|
|
|
(4) |
粗じん用フィルタ
---- 高性能フィルタ ----- 中性能フィルタ |
|
|
|
|
(5) |
粗じん用フィルタ
---- 中性能フィルタ ----- 高性能フィルタ |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題73 |
空気浄化装置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
静電式は、金属フィルタ面へ粉じんを衝突させる方式である。 |
|
|
|
|
(2) |
HEPAフィルタは、クリーンルームで用いられる。 |
|
|
|
|
(3) |
自動更新型フィルタは、ロール状のろ材を汚れに応じて自動的に巻き取る方式である。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
エアフィルタの性能は、定格風量時における除去率、圧力損失、除去容量で示される。 |
|
|
|
|
|
|
(5) |
吸着法は、吸着剤で有害ガスを吸着除去する方式である。 |
|
|
|
|
|
| 問題74 |
ポンプに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
歯車ポンプは、吐出圧力に比例して流量が変化する。 |
|
|
|
|
(2) |
ダイヤフラムポンプは、容積型に分類される。 |
|
|
|
|
(3) |
インラインポンプは、配管の途中に取り付けられる。 |
|
|
|
|
(4) |
多段渦巻きポンプは、2枚以上の羽根車を直列に組み込むことで、高揚程を確保できる。 |
|
|
|
|
|
|
(5) |
渦巻きポンプは、ターボ型に分類される。 |
|
|
|
|
|
| 問題75 |
弁類に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
バタフライ弁は、軸の回転によって弁体が開閉する構造である。 |
|
|
|
|
(2) |
安全弁は、一般に圧力の高い容器や配管に設置される。 |
|
|
|
|
(3) |
玉形弁は、弁体と弁座の隙間を変えて流量を調節する形式である。 |
|
|
|
|
(4) |
ボール弁は、抵抗が少なく流量調整ができる。 |
|
|
|
|
(5) |
リフト式逆止弁は、立て配管に取り付ける。 |
|
|
|
|
|
| 問題76 |
温熱環境要素の測定器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
アスマン通風乾湿計は、気流及び熱放射の影響を防ぐ構造となっている。 |
|
|
|
|
(2) |
サーミスタ温度計は、温度により電気抵抗が異なることを利用するものである。 |
|
|
|
|
(3) |
アスマン通風乾湿計の湿球を湿潤させる液体には、アルコール水溶液を用いる。 |
|
|
|
|
(4) |
バイメタル式温度計は、張り合わせた金属の膨張率の差を利用するものである。 |
|
|
|
|
(5) |
自記毛髪湿度計は、低湿及び高湿。高温の環境での測定は避けるべきである。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題77 |
気流測定法及び風量測定法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
熱線風速計のセンサは、形状による指向特性に注意して測定を行う。 |
|
|
|
|
(2) |
L型ピトー管は、全圧と静圧の差から動圧を求めて風速を算出する。 |
|
|
|
|
(3) |
空調吹出風量の測定には、補助ダクトを用いることが望ましい。 |
|
|
|
|
(4) |
ダクト内風量の測定装置に、オリフィスを用いることができる。 |
|
|
|
|
(5) |
ダクト内風量の測定に、トレーサガス減衰法が用いられる。 |
|
|
|
|
|
| 問題78 |
室内空気環境の管理における浮遊粉じんの測定法と測定器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
測定法には、質量濃度測定法と相対濃度測定法がある。 |
|
|
|
|
(2) |
標準となる測定法は、ローボリウムエアサンプラ法である。 |
|
|
|
|
(3) |
透過光法は、粉じん捕集前と捕集後におけるろ紙の光の透過率の変化量から粉じん濃度を求める方法である。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
相対沈降径は、同じ沈降速度を有する比重1の球の直径である。 |
|
|
|
|
(5) |
光散乱法を用いた粉じん計の出力値ODとは、光学密度をいう。 |
|
|
|
|
|
| 問題79 |
ホルムアルデヒド測定法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
簡易測定法には、アクティブ法とパッシブ法がある。 |
|
|
|
|
(2) |
DNPHカートリッジ捕集-HPLC(高速液体クロマトグラフ)法は、妨害ガスの影響をほとんどうけない。 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
光電光度法は、妨害ガスの影響をほとんど受けない。 |
|
|
|
|
(4) |
AHMT法は、妨害ガスの影響をほとんど受けない。 |
|
|
|
|
(5) |
検知管法は、酸性物質やアルカリ性物質の影響を受ける。 |
|
|
|
|
|
| 問題80 |
空気環境における、汚染物質とその測定方法との組み合わせとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
VOCs
---------- GC/MS法 |
|
|
|
|
(2) |
窒素酸化物 ------
化学発光法 |
|
|
|
|
(3) |
いおう酸化物 -----
ザルツマン法 |
|
|
|
|
(4) |
オゾン
----------- 紫外線吸収法 |
|
|
|
|
(5) |
一酸化炭素 ------
検知管法 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題81 |
空気調和設備の試運転調整に関する次の記述のうち、最も不適当なものは、どれか。
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
ポンプの単独運転中にポンプを発停し、停止中に空気抜きから空気を抜き、水配管中の空気を完全に除去する。 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
機器と電動機を結んでいるベルト又はカップリングを外し、電動機の無負荷運転を行い、異常の有無を確認する。 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
冷媒配管は、配管内へ二酸化炭素を吹き込み、管内の異物や水分を外部へ吹き飛ばす。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
水配管は、管内の排水が澄んでくるまでブローし、配管用炭素鋼管(黒管)使用の場合は清掃終了後、水を抜いておく。 |
|
|
|
|
|
|
(5) |
機器の回転部分の軸受などにグリース、潤滑油を供給し、数時間運転した後、油を取り替えてをく。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題82 |
空気調和設備の運転及び管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
遠心冷凍機では、運転中に蒸発器が大気圧以下となるので、気密性に注意が必要である。 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
吸収冷凍機では、腐食による劣化と真空度低下が課題である。 |
|
|
|
|
(3) |
ボイラでは、運転中の過熱事故に注意を要する。 |
|
|
|
|
(4) |
開放型冷却塔では、蒸発、飛散及びブローのために、一般に循環水量の2%程度の補給水量を見込んでおく必要がある。 |
|
|
|
|
|
|
(5) |
加湿装置は、建築物環境衛生管理基準に基づき、使用を開始した後、2ヶ月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検する。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題83 |
音に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
コインシデンス効果が生じると、壁体の透過損失が増加する。 |
|
|
|
|
(2) |
一般に部屋の容積が大きいほど、残響時間が長くなる。 |
|
|
|
|
(3) |
点音源からの音圧レベルは、音源からの距離が2倍になると6dB減衰する。 |
|
|
|
|
(4) |
開放された窓の吸音率は、1である。 |
|
|
|
|
(5) |
1オクターブ幅とは、周波数が2倍になる間隔である。 |
|
|
|
|
|
| 問題84 |
1台80dB(A)の騒音を発する機械を、測定点から等距離に8台同時に稼動させた場合の騒音レベルとして、最も近いものは次のうちどれか。
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
86dB(A) |
|
|
|
|
(2) |
89dB(A) |
|
|
|
|
(3) |
92dB(A) |
|
|
|
|
(4) |
166dB(A) |
|
|
|
|
(5) |
172dB(A) |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題85 |
床衝撃音に関する記述のうち、重量床衝撃音の説明に該当する組合せとして、最も適当なものはどれか。
ア.衝撃源自体の衝撃力が低周波数域に主な成分を含む。
イ.物の落下による衝撃力が小さく、衝撃源が硬い。
ウ.床仕上げ材の弾性が大きく影響する。
エ.対策として、床躯体構造の質量の増加が挙げられる。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
ア と イ |
|
|
|
|
(2) |
ア と ウ |
|
|
|
|
(3) |
ア と エ |
|
|
|
|
(4) |
イ と ウ |
|
|
|
|
(5) |
イ とエ |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題86 |
防振に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
荷重による防振材のひずみは、無負荷時の10%以上にならないようにする。 |
|
|
|
|
(2) |
防振系の基本固有周波数は、機器の加振周波数に対してできるだけ大きく設定する必要がある。 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
機器を防振する場合、耐震上の対策から耐震ストッパを取り付けることが多い。 |
|
|
|
|
(4) |
実際の防振効果は、一般に中、高周波領域で理論値(完全剛体・1質点)より低下する。 |
|
|
|
|
|
|
(5) |
適正な固有周波数を得るため、極力均等に荷重がかかるように防振材を配置する。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題87 |
点光源直下2.0mの水平面照度が200
lxである場合、光源直下0.5mの水平面照度として、正しいものは次のうちどれか。
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
50 lx |
|
|
|
|
(2) |
400 lx |
|
|
|
|
(3) |
800 lx |
|
|
|
|
(4) |
1600 lx |
|
|
|
|
(5) |
3200 lx |
|
|
|
|
|
| 問題88 |
照明に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
(1) |
白熱電球は、温度放射に伴う発光を利用している。 |
|
|
|
|
(2) |
LEDとは、発光ダイオードのことである。 |
|
|
|
|
(3) |
ブラケットは、天井に埋め込む照明器具である。 |
|
|
|
|
(4) |
高圧ナトリウムランプは、HIDランプの一種である。 |
|
|
|
|
(5) |
コーブ照明は、建築化照明の一種である。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 問題89 |
光源の設計光束維持率に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。
光源の設計光束維持率は、[ ア
]に伴う光源自体の光束の変化による照度低下を補償するための係数であり、使用する光源の初期光束と[ イ ]の比で表わされる。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
周囲温度の変化
------- 使用直後の光束 |
|
|
|
|
(2) |
周囲温度の変化
------- 100時間点灯後の光束 |
|
|
|
|
(3) |
点灯時間の経過
------- 100時間点灯後の光束 |
|
|
|
|
(4) |
点灯時間の経過
------- 光源を交換する直前の光束 |
|
|
|
|
(5) |
周囲温度の変化
------- 光源を交換する直前の光束 |
|
|
|
|
|
| 問題90 |
次の湿り空気線図上に示した空気状態の変化の3つのプロセスとその加湿装置との組合せとして、最も適当なものはどれか。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒸気加湿 |
水加湿 |
パン型加湿 |
|
|
|
(1) |
1
----------- 2 ----------- 3 |
|
|
|
|
(2) |
3
----------- 1 ----------- 2 |
|
|
|
|
(3) |
1
----------- 3 ----------- 2 |
|
|
|
|
(4) |
2
----------- 3 ----------- 1 |
|
|
|
|
(5) |
3
----------- 2 ----------- 1 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|